講座概要
日本の大企業にとって米国市場は、今後とも持続的な成長が見込めることから、ますます重要性が高まっています。そうした中、米国子会社の経営で最も難しいのが「人の管理」です。日本から役員や管理職を派遣しても、なかなか米国での人事問題に適切に対応できていないのが現状です。米国と日本では、法制面の違いだけでなく、人事管理に対する考え方やプロセスが根本的に違う点を十分に認識しておく必要があります。今後の米国子会社の一層の発展や米国での企業買収に備えて、日本本社の幹部に米国の人事管理制度全体を理解してもらうため本講座を開設しました。
本講義は、Zoom(ウェビナー)を利用してWebで配信いたします。
ご参加に伴い下記URLをご確認ください。
https://www.rosei.jp/seminarstore/seminar/zoom
【本講座のポイント】
①米国子会社の管理に不可欠な米国での人事制度全般の知識を提供します
②日米の人事制度につき、どこが、なぜ異なるのか法律の違いを基に説明します
③将来米国子会社に役員や管理職として赴任される方にも役立ちます
講座内容
I 定年制度の有無
米国の年齢による差別禁止法の下では、定年制度はおろか、役職定年制、60歳再雇用制度などもすべて違法。
Ⅱ 採用制度の相違
日本では新卒定期採用が中心で、ポジションによる初任給の差はないが(メンバーシップ型雇用)、米国では空きポジション発生時の中途採用が中心。給与はポジションごとに異なる(ジョブ型雇用)。
Ⅲ 給与決定制度の相違
日本では年次や社内の職階・格付けによる給与決定方式だが、米国では職種や経験年数、学歴、資格の有無に基づく人材市場での市場価格の影響が大きく、他社動向に即応することが求められている。
Ⅳ 従業員の離職対策の重要性
大量退職の時代を迎え、部下がいつ辞めるか分からない雇用状況の中、ワンオンワン・ミーティング等による部下のキャリア形成へのサポートが必要 。
Ⅴ 人事評価制度の相違
米国では、評価次第で解雇されることもあり得るので、日本よりも客観性や納得性が求められる。またワンオンワン・ミーティング等を通じた日常の上司・部下間のコミュニケーションが重要。
Ⅵ 社内人事異動やローテーション制度
米国では、社員の大部分がジョブ型雇用でそれぞれ専門を持っているため、日本のような定期的な人事異動や一方的な発令は難しい。
Ⅶ 就業規則や人事慣例
訴訟社会といわれる米国では就業規則や人事慣例は、訴訟対策上、日本よりもはるかに大きな役割を果たしている。また、州ごとに法律が異なる部分があるため、複数の州に事業所や工場を持つと異なる人事規則を適用せざるを得ないケースが出てくる。
Ⅷ 解雇や人員整理に対する取り組み(アンダーパフォーマーへの対応)
ジョブ型雇用では一人ひとり職務内容と給与が決まっているため、職務遂行能力不足は、解雇につながることもある。(日本のように配置換えや職務分担の再配分が容易でないため)したがって管理職に対する適切な解雇手順の教育が必要。また過剰な人員は希望退職者募集や人員整理で対処する。
Ⅸ 米国固有の人事問題
州雇用法の多様性による休暇制度等の州ごとの相違、州による給与水準の相違、マリファナ合法化による雇用上の問題、採用前の犯罪歴調査に関する制限等。
Ⅹ 社内教育制度
社員の離職率が高いため社員教育はできるだけオンディマンド化し、いつでもだれでも受けられるような仕組みが重要。
講師プロフィール
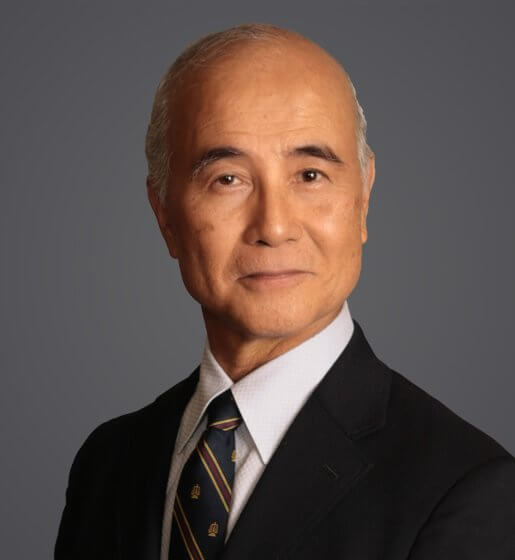
オグルツリー・ディーキンス法律事務所 インディアナポリス事務所 インディアナ州弁護士 (1996年)、ワシントン州弁護士 (2021年)
本間 道治 氏
オグルツリー・ディーキンス法律事務所 インディアナポリス事務所 インディアナ州弁護士 (1996年)、ワシントン州弁護士 (2021年)
本間 道治 氏
【略歴】
一橋大学社会学部卒業。三井不動産株式会社において人事研修部門、広島支店マンション開発担当、社長秘書、会長秘書、秘書室課長、都市開発事業部事業企画課長等の職務を経験し、1991年3月同社退職。1994年12月米国オハイオ州立シンシナティ大学ロースクールJ.D.課程卒業。2002年8月からオグルツリー・ディーキンス法律事務所に所属。著書『40歳からの米国での挑戦―米国で弁護士を目指す』(Amazon)。


 セミナー
セミナー オンデマンド
オンデマンド 企業研修
企業研修 お買い物ガイド/
お買い物ガイド/ セミナーストアへの
セミナーストアへの セミナーストアへのお問い合わせ
セミナーストアへのお問い合わせ



 労政時報編集部
労政時報編集部 労務行政研究所
労務行政研究所

