
撮影=小林由喜伸
木村達央 きむら たつお
株式会社ジャパンイマジネーション 代表取締役会長
1948年東京都生まれ。71年学習院大学経済学部卒業後、三菱商事に入社し、主に経理業務を担当。76年株式会社デリカ(ジャパンイマジネーションの前身)入社。営業部長、専務などを経て90年に代表取締役社長に就任、2010年代表取締役会長に就任。社長在任時から「組織はフラット、考え方はシンプル」を掲げる。
趣味は物見遊山で、主な行き先は「イタリア」「温泉」「飛鳥地方」だという。
10代や20代女性に大人気の「セシルマクビー」で知られる。
ギャル向けブランドとしてブレイク以来、人気を16年間も継続。
変化対応力を高めることで、ブランドと会社の生き残りを目指す。
取材構成・文=高井尚之(◆プロフィール)
「社会のニーズのある仕事を、いい人を集めて、一生懸命やってもらう」
ジャパンイマジネーション会長の木村達央さんが、社長時代から掲げる経営方針だ。
もっともこの言葉、本人のオリジナルではない。
組織も思考も「シンプル」がいい
今やベテラン経営者の木村さんも、社長に就任したのは42歳のとき。20代で総合商社勤務から家業に転じ、やがて役員の階段を上ったが、まだ経営方針は定めきれていなかった。
そんなとき、冷凍食品大手の加ト吉(=現テーブルマーク)会長の講演を聴く。同会長が話していたのが、冒頭の言葉だった。就任早々の青年社長は「これだ」と思う。
「商社にいた若いころから、自分なりに経営学を勉強していました。でもこの言葉を聞いて、ストンと腹に落ちたのです。『ああそうか、会社を経営するというのは簡単だな』と」
そう感じたのは20年以上前だが、現在でも通じる話だろう。
さまざまな会社の現場と向き合っていて感じるが、企業の課題を、わざわざ難しく捉えるケースも目立つ。販売やマーケティングでも、人事や総務でもそうだ。
多くは、競合他社や欧米型の手法をベンチマーキングした結果、「森づくり」よりも「植える木」にこだわり、大局的な視点を見失ってしまうのだ。
現在のジャパンイマジネーションは、年間売上高が約230億円、従業員が約1200人の規模となったが、組織体制は「営業本部」「管理本部」の2本部のみ。取締役も3人だけだ。
木村さんは、次のように話す。
「これだけ変化の激しい時代ですから、できるだけ身軽で、考え方も組織もシンプルにしておく。そのほうが、時代対応力のある会社になれると思います」

常識さえ外さなければ、どんな仕事も、基本的なところは変わらない
従業員約1200人のうち、約1100人が店舗販売スタッフ(FA[ファッションアドバイザー])である同社は、メディアからは“店長産業”とも呼ばれる。
毎日店を訪れて買い物をするお客と向き合い、商品の変身や進化につなげる。こうした「顧客起点」や「店頭起点」をビジネスモデルにして成長してきた。店長の力量によって売り上げも左右されるのだ。
「ここまで店長に裁量と権限・責任を与えて、情報の収集と発信役を任せている会社は、レディスブランドでは珍しい」(ファッション関係者)という。
だからだろう。木村さんは「社長や会長も含めた本部の役割は店長のサポーターです」と語る。
実績を上げた若手を抜擢
「若い女性に訴求するレディスアパレル」という業種の特性もあり、ジャパンイマジネーションは創業66年の老舗企業でありながら、従業員の平均年齢は驚くほど若い。
全社の平均で24.6歳、女性に限っていえば23.9歳という若さだ(もっともこれは、従業員の9割以上がFAという、数字のマジックもあるが)。
主力ブランド「セシルマクビー」の販売関係者は、店長に次ぐ役職である「チーフクラスの底上げが課題」とも話す。この場合のチーフクラスとは、入社2~3年目のことだ。
特に数字で結果が現れる営業部門は、業績を重視する。「人柄がよくて、実績を上げた人をとことん評価する。学歴も出身校も性別も関係ない」をポリシーに、時に抜擢人事を行う。
その象徴が、現社長の小嶋裕之さんだ。20歳で入社後はFAとして店舗に配属。まだセシルマクビーが飛躍する前の時代だったが、いきなり月間売り上げ1000万円を記録する。店長としても業績を上げると、セシルマクビーのブランドマネジャーに抜擢。
ここでブランドを刷新して大ブレイクを果たすと、31歳で部長となる。そして取締役、常務、専務と出世の階段を駆け上がり、43歳で社長に就任した。
業績が数値で現れにくい管理部門には、金融や流通など他社で実績を積んだ50代が幹部社員を務めるケースも多いが、中間管理職ではプロパーもいる。
人事係長を務める藤原麗佳さんは、20歳でアルバイトのFAとしてスタートしたが、その後に社員となり、セシルマクビーのチーフ、店長を経て、現場経験を買われて本社人事スタッフに抜擢された。現在は、新卒の採用担当のほか、社員研修の講師も務めている。
一連の人事は、木村さんの経営方針でもある。
「ファッション業界で元気な会社は、40代の経営者のもと、30代が中心となって、20代の女性社員が生き生きと働く」を掲げ、それを実践している。

自社ブランドに誇りを持って働けているかどうか
ここで紹介したように、同社社員の多くは入社時からエリートだったわけではない。
今年の入社式を見学させてもらったが、新入社員であっても、髪色も髪型も服装も自由だ(ただし奇抜なのはNG。ファッション業界人としての“こだわり”がドレスコードだ)。今の時代の若者らしく、外見は派手に見えても中身は真面目なタイプが多い。
それが入社後の実戦で鍛えられ、ファッションブランドの戦力として育っていく。
ある女性FAの言葉を借りると「華やかだけど、めちゃくちゃ体育会系」――。店舗では挨拶や言葉遣いなど上下関係もきちんとしており、「毎日部活をやっている感じ」だとか。
経営者の「こだわりすぎ」はダメ
前回、ジャパンイマジネーションは「商品」と「経営」を分けて運営してきた――という話を紹介したが、これも同社が生き残れた理由の一つだろう。
「商品」に関する木村さんの姿勢は明快だ。「私はファッションのことは全然分からない」と語り、若手に任せる。そう言いながらも、本人の取材時の服装(毎回こだわりを感じる)を見て、業界に対する分析を聞けば聞くほど、「全然分からない」とは思えない。
そこにあるのは、「経営者のこだわりを消す」という姿勢だ。木村さんはこう説明する。
「ファッション業界でダメになる会社は、『社長が商品開発にイニシアティブを持つ』というケースも多いのです。現在のように、お客様が主導権を持つ時代に、経営者のこだわりが強すぎると、変化への対応も鈍ると思います」
ここまで消費が成熟し、景気が低迷している現在では、生活者は「これは」というものにだけサイフのヒモを開く。いくら送り手側がこだわっても、自分にピンとこなければ買わない。
小売業ではなく、製造業のケースでも考えてみよう。
業種が違えども、メーカーには自社の得意な技術がある。ビジネス用語でいう「基盤技術」(キーテクノロジーやコアテクノロジー)だが、自社の技術にこだわりすぎると、やはり経営環境の変化への対応が遅れる。
逆に、こだわりが強くない会社では、一定の技術を組み合わせてユニークな商品やビジネスモデルを創り出す。現在の大手電機メーカーの業績で、明暗が分かれる理由もそこだ。

必要なのは、渋谷109的な変わりの早さ、いい加減さ、身軽さ
ジャパンイマジネーションの商品は、トレンドをきちんと押さえつつ、トンガりすぎない“サジ加減”もしている。
主力であるセシルマクビーは「東京リアルクローズの代表ブランド」とも呼ばれる。東京リアルクローズとは“手の届く身近なおしゃれ普段着”と解釈されるが、欧米の伝統的なファッションショーで披露される服は、話題性はあるが、時に奇抜で街で着る感覚に欠ける。現在の目の肥えた生活者は、そうした憧れよりも着やすさを重視する。
「ファッションのことは全然分からない」という木村さんも、当たり前だが、経営の根本にはこだわる。特に重視するのが、売り上げをはじめとする業績データだ。これは、ほぼ毎日チェックする。
「主に『売り上げ』『粗利』『在庫』などを見ます。これらのデータは前年同月との比較だけでなく、必ず同じ曜日と重ねて、日ごとの数字を見ながら判断します」
プリントアウトした表に数字を記入して比較する。「やり方は任せながらも、結果は重視する」という姿勢を貫く。
外部の「知」が刺激になった
かつてセシルマクビーは“山の手お嬢様”路線の保守的なブランドだった。それが1996年に、木村さんがよく語る「渋谷にセクシーカジュアルの突風が吹いた」という時代の風に乗って、大ブレイクを果たしたが、実はそれまでの布石もあった。
会社として、2年前の94年ごろからブランドの改革を進めていた。競合との差別化が十分ではなく、売り上げが伸び悩んだためだ。
相前後して、新しいブランドも開発する。例えば「オクシード」「リマージュ」「アルガーファ」「スパイク」といったブランドが世に送り出された。
セシルマクビー以外に、現在残っているブランドはなく、結果だけ見れば失敗だったが、「現状を変えよう」という意識が社内に芽生えた。
特に大きかったのは「スパイク」ブランドの経験だ。これは同社で初めて、外部スタッフである小松健樹さん(後に、渋谷109の人気ブランド『ラブボート』をプロデュース)に依頼して立ち上げた。木村さんはこう振り返る。
「今までの社内では考えられなかった、小松さんの斬新な発想に衝撃を受けました。それに触発された若手社員が、感性を生かして新しいことをやり始めたのです。その1人が小嶋(セシルマクビー飛躍の立役者で現社長)でした」

新しいことを始めることの難しさを乗り越えるきっかけがあった
小売業であれ、製造業であれ、常に新たなテーマに前向きに取り組む企業風土があってこそ、組織もヒトも活性化される。
「私はもともと、あまり主義主張を持たないのです。何か提案されると『ああ、面白いじゃない。やってみよう』というタイプですから」と、木村さんは自己分析する。
前回紹介したように、ジャパンイマジネーションのブランドは、今でも「製造小売り(SPA)」ではなく、取引先メーカーが提案する「品ぞろえ型」にこだわる。
セシルブランドを刷新した当時も、新たな取引先の斬新な提案で、面白い商品が次々に生まれたという。「製造小売り」と「品ぞろえ型」手法の甲乙は簡単にはつけにくいが、外部の「知」によって刺激を受けるという点では、品ぞろえ型に軍配が上がりそうだ。
目指すのは「人が集まる会社」
セシルマクビーを起爆剤に成長してきたジャパンイマジネーションだが、現在、セシルの関係者は「ブランドの血が薄まったので何とかしないと」と、危機感を抱く。
かつての“ギャル向け”から、40代や50代の“大人受け”するブランドへと幅が広がった結果、逆に特徴が弱まったからだ。
社内では、もう一度「セシルらしさ」を再徹底するための、改革に乗り出している。例えば「通販限定商品」を開発すれば、上の世代に向けたブランド開発も検討する。
取引先のさまざまな要望に対応するため、社内組織も再編した。従来は1人だったMD(マーチャンダイジング職)に、商品MDを設けて3人体制にしたり、新たに店舗MDを設けて店舗間のバランスを取ったりするなど、戦略的な組織に変えたのだ。
常に変身し続けることで成長してきたセシルマクビーとジャパンイマジネーションが、変わることをやめれば、ブランドの、そして企業としての衰退につながる。木村さんは「セシルに次ぐブランドの早期育成も急ぎたい」と話す。
「今後も1~2年に一つぐらいは新しいブランドを出していきたい。なぜかといえば、ファッションとは変化そのもの。『鮮度』こそ競争力のすべてだからです」
世間でよく使われる「先行き不透明」という言葉にも違和感を持つ。
「10年後や20年後の経済環境がどうなっているかを予測するのは無理でも、日々の仕事に没頭してお客様と向き合っていれば、今後の先行きは分かるのではないでしょうか」
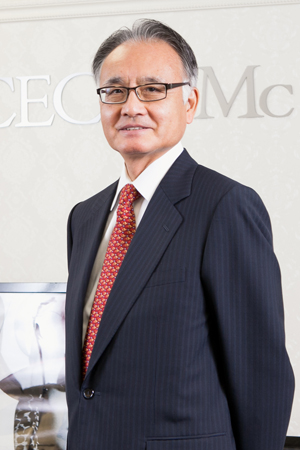
いろいろなことにチャレンジし、自分なりの方向感覚を培っていくことが大事
木村さんには、具体的な売上目標よりも目指す道がある。冒頭に掲げた経営方針とも関連するが、「人が集まる会社にしたい」というものだ。
「この会社で働きたいという人が集まり、取引をしたいという人が集まり、お客様が集まる――といった意味です。そうなれば業績は自然に上がると考えています」
もちろんそのためには、商品と会社の魅力づくりが大切だ。
危機感や問題意識を持ちながら、「顧客起点」や「店頭起点」を真摯(しんし)に行い、明日のお客が求める傾向をつかむ。それに見合った商品や販売方法を提案して、お客の支持を高める。
さらに「CSR」(企業の社会的責任)の視点も踏まえ、会社の透明度も磨き続ける。
これからもそのやり方で、ブランド人気と会社経歴の最長不倒を目指すのだろう。
■Company Profile
株式会社ジャパンイマジネーション
・創業/1946(昭和21)年 ・設立/1957(昭和32)年
・代表取締役会長 木村 達央 代表取締役社長 小嶋 裕之
・本社/東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー13F
(TEL) 03-3372-8151(代)
・事業内容/レディスファッションの企画・販売
・代表商品/『セシルマクビー』『アンクルージュ』など
・従業員数/1171人(2012年9月30日現在)
・企業サイト http://www.j-im.jp
◆高井尚之(たかい・なおゆき)
ジャーナリスト。1962年生まれ。日本実業出版社、花王・情報作成部を経て2004年から現職。「企業と生活者との交流」「ビジネス現場とヒト」をテーマに、企画、取材・執筆、コンサルティングを行う。著書に『「解」は己の中にあり 「ブラザー小池利和」の経営哲学60』(講談社)、『なぜ「高くても売れる」のか』(文藝春秋)、『日本カフェ興亡記』(日本経済新聞出版社)、『花王「百年・愚直」のものづくり』(日経ビジネス人文庫)など。近著に『セシルマクビー 感性の方程式』(日本実業出版社)がある。




