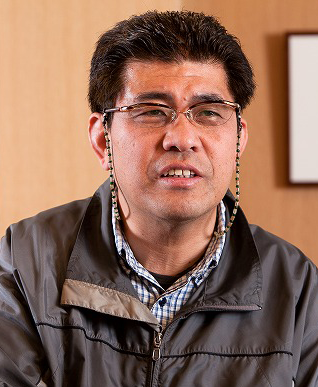 撮影=戸室健介
撮影=戸室健介
廣川雅一 ひろかわまさかず
株式会社ヒロカワ製靴・代表取締役社長
1956年東京都生まれ。小学生から家業を手伝いながら育ち、
1975年にヒロカワ製靴に入社、下ごしらえや仕上げなど靴作りの
各現場で修行。営業を経験後、1987年に専務、2006年に社長に就任。
上野、銀座、大阪などに直営店を持ち、スコッチグレインの品質管理と
ともに、靴選びの大切さや履く楽しさなども伝えている。
手間ひまをかけた製法で、自社ブランドの靴作りを続けて34年。
最近は人気エリアへの出店、話題商品の製作にも力を入れている。
高品質でもお高くとまらず敷居が低い。それもまた下町気質だろう。
取材構成・文=高井尚之(◆プロフィール)
日本中の注目を集めた、下町の空にそびえる高さ634メートルのタワー。
東武鉄道が建設した「東京スカイツリー」の開業と同時に、隣接する東京スカイツリータウン「東京ソラマチ」もオープンした。312の店舗が入居する巨大ショッピングモールだ。ブランド靴「スコッチグレイン」も店を構える。

5月22日、東京ソラマチ1階のイーストヤードに同社で8店目となる直営店を開店
地元「ソラマチ」出店のねらい
「しばらくは観光客がほとんどでしょうが、開業直後の喧騒が落ち着いてから、どんな客層になるかはわからない。でも、私たちのやることは変わりません」
東京ソラマチのイーストヤード1階にある店舗前。行き交う来場客を見守りながら、スコッチグレインを手掛ける廣川雅一さん(ヒロカワ製靴社長)は、淡々と話す。
廣川さんが話す「やること」とは、良質の靴作りを続け、お客の足、そしてフィーリングに合った商品を提供するという意味だろう。

17.5坪の店舗に並ぶこだわりの製品が華やかさを演出する
今年(2012年)春、首都圏では大型商業施設が相次いで誕生した。まず4月13日には「三井アウトレットパーク木更津」(千葉県木更津市。171店)が開業し、同19日には「ダイバーシティ東京プラザ」(東京都港区。154店)がオープン。そして5月22日に、この東京ソラマチ(東京都墨田区。312店)が開業した。ソラマチに入居するショップの中でも、ヒロカワ製靴は最も近い墨田区・堤通に本社を置く。
もともと墨田区はモノづくりの街。区も地元のモノづくりを戦略的に紹介し始めた。
その一つが「すみだモダン」と呼ぶ区内ブランドの認定だ。これは応募作品の中から、すみだらしい逸品を審査・認定するもの。江戸時代から多くの職人が暮らし、それ以来長年にわたり、墨田区の職人が生み出した製品が暮らしを支えてきたことをPRする目的だ。
いわゆる「ご当地活性化策」だが、そのキッカケが東京スカイツリーの建設だった。観光地として地味だった区に、スカイツリー効果で光が当たる機会を利用したのだ。
2011年には商品分野で23商品、飲食分野で14メニューが認定されている。
例えば、商品では「革風呂敷」(二宮五郎商店)、「はさみ」(石宏製作所)、「ドレスシャツ」(丸和繊維工業)などと共に、ヒロカワ製靴のスコッチグレイン「スパイダー」も選ばれた。
http://sumida-brand.jp/archives/2011-12-2-brand2011
「スコッチグレインのスパイダーは『すみだモダン』認定品ですが、さまざまな革を使ったスパイダーもあります。ソラマチ店限定モデルとして、高品質の革製造メーカー(タンナー)として定評のある栃木レザーのタンニンなめしの革で作ったスパイダーを販売しています。使いこなすほどに渋みのある色に変化して、いい雰囲気が出てくるんです」
こう説明する廣川さん。あえて“お墨付き”を掲げ、区の活動を後押しする役割も担う。
スパイダーは、革を抜く際に出る革片や首周り部分の残り革を使った商品だ。甲革を細かいパーツで組み合わせ、パッチワークデザインとして生かした。デザインの面白さと、残った革をムダにしないエコロジーさの両面から訴求している。

甲革にはフランス・アノネイ社の高級カーフの残革を使用。手前のものはモルト仕上げを施したもの

ソラマチ店限定の栃木レザーのなめし革で作ったスパイダーは、茶と黒の2色を用意
パンダの靴を真面目に作る
墨田区のお隣、台東区の上野動物園に新たなパンダ「リーリー」(オス)と「シンシン」(メス)がやってきたのは昨年(2011年)2月のこと。4月1日から一般公開されると、訪れるお客が急増。2011年度(11年4月~12年3月)の年間来園客数は470万人を超え、2010年度の約267万人に比べて200万人以上も増えた。
「やはり上野にはパンダが似合う」(地元の商店街幹部)と歓迎されるように、上野はパンダがいてこそ活気づく。40年前(1972年)の初来日では“パンダフィーバー”が社会現象となり、1974年度には過去最高の年間約764万人もの来園者が上野動物園を訪れた。動物園の後は、上野の街で食事をして土産を買い、地元商店街も大いに潤った。
博物館や美術館、西郷さんの銅像で知られる街も、パンダ効果で再び親子連れや若いカップルが増えた。松坂屋上野店ではピンク色の「さくらパンダ」が人気を呼び、地元のカフェには、パンダデザインのラテアート(カフェラテに描く模様)も登場した。
そんな中、ヒロカワ製靴でも新たな商品「パンダシューズ」を開発。おなじみの白と黒のツートンカラーを再現したインパクトのあるデザインだ。動物園のお膝元、スコッチグレインecute上野店で限定販売(3万9900円)している。
「ウチが入店するエキュート(上野駅・駅ナカ)の他の店でもパンダ関連商品が増えていたので、何かやろうと考え、遊び心で企画しました」と廣川さんは笑う。
当初はディスプレー用だったが、やがて通行人や来店客の間で評判となり「いくらで販売しているのか」という問い合わせも増加。人気に応えて昨年9月に受注生産を始めた。

スコッチグレインecute上野店では、店舗スタッフに一声を掛けると、実際に履いた状態で写真を撮らせてくれる
つま先部分にパンダの顔を描き、目や舌は牛革を貼り付けた。この顔を表現するために、数十種類のパンダの写真から研究したそうだ。
ヒモは黒色と白色の2種類を用意し、その日の気分で取り換えもできる。4万円近い高価格だが「これまでに十数足が売れた」という。
ちなみにタレントのルー大柴さんも購入者の1人。昨年のクリスマスプレゼント用のカタログで同商品を知って気に入り、店を訪れて注文。年明け1月に完成品を手に入れた。
「ディスイヤー(今年)はこのパンダシューズ君とトゥギャザー(一緒)でジャパンを駆け巡ります!!」と得意の“ルー語”を用い、公式ブログで紹介したほどだ。
社内のムードが前向きになる
パンダシューズは、スコッチグレインにとって異色のモノづくりだろう。これまで「カッコイイ」靴にこだわってきた会社が、「カワイイ」靴作りにも挑戦した。
ここで紹介したスパイダーやパンダシューズといった新商品の開発は、実は売上金額以上に大きな効果がある。社内の雰囲気だ。
どんな業種でもメーカーの場合、新商品が発売されれば、社内のムードが前向きになる。
「スパイダーも最初は『残った革で靴を作ろうよ』と言って、企画が始まりました。型を取った残りの革を残革(ざんかく)といいますが、もともと価値のある高級革です。これを革小物にするのではなく、靴に生かすことを考えようという視点からスタートしたのです」
ヒロカワ製靴では人材教育の一環として、若手の有志による「企画チーム」がある。例えば、年2回、直営店で行うセールで発売される商品を企画するチャンスが与えられる。
日々の業務を終えた後に、有志が集まり、話し合いを重ねながら企画を練る。限られたベテラン社員だけで企画をすると、若手のモチベーションは上がらない。
こうした取り組みはやる気にもつながる。これを始めた廣川社長に、従業員をその気にさせるコツを聞いてみた。
「まずは目標を達成したら、きちんと評価してあげることでしょう。人間は誰でもほめられるとうれしいものです。そして作業中は、状況に応じて声を掛ける。壁にぶつかり悩んだ時は、アドバイスも心掛けています。私も職人の1人だと思っており、試行錯誤しながらモノづくりに取り組む職人の気持ちになって考えているつもりです」
企画チームでは、デザインを考えて革を選び、サンプルを作った段階で、廣川さんへの「社長プレゼン」が待っている。ブランドイメージや採算性の点から不採用も多いそうだが、そこでヘコたれずに再挑戦した中から商品化の道も開かれる。
採用の決め手は「今までにないもの、でもスコッチグレインらしさ」だと言う。いい意味で業界の常識に染まっていない若手だからこそ、表現できる世界もあるはずだ。

奥にあるのがレディースシューズの印伝モデル。印伝とはインド伝来の革の染加工で、美しい文様を生み出す
モノづくりから「ブランドづくり」に
人気エリアへの出店やユニーク商品で話題を呼んでも、「日本一真面目な靴作り」という軸足は変えないスコッチグレイン。すべての靴に手間のかかる「グッドイヤーウェルト製法」を採用しており、それはたとえ遊び心で作った、パンダシューズでも同じだ。
本社近くに点在する自社工場は、「革の裁断」「ミシン縫い」「靴底の貼り付け」「すくい縫いや出し縫い」(二度縫いするのもグッドイヤーウェルト製法の特徴)といった作業別に分かれ、約100人の職人が黙々と作業をする。
頑固なモノづくりを続ける一方で、最近の廣川さんが力を入れるのはブランドづくりだ。
目指すのは、スコッチグレインの世界観を保ちつつ意欲的な活動を続けて、一見のお客から固定ファンに変えること。ウイスキーで靴を磨く「モルト・ドレッシング」の実演販売も、長年履き続けた靴の修理を行うのも、その一環でもある。
ビジネス現場では「商品は真似されるけどブランドは真似されない」と言われる。ヒロカワ製靴にはスコッチグレインのブランド哲学をまとめた「コンセプトブック」もある。廣川さんがこだわる革の選別から始まり、グッドイヤーウェルト製法の流れも載っている。
著名なカメラマンに撮影を依頼して各作業を追ってもらい、豪華本の体裁で制作した。ちなみに費用は1冊約10万円もかかったという。ブランドのバイブルとして、国内各地で運営するスコッチグレイン直営店にも置く。
ところどころでこうした論理性にこだわりつつ、決して気難しいブランドにはしない。
親しみやすさを演出する手法が「敷居の低さ」だ。高級靴であっても手の届かない価格にはせず、中心価格帯を2万9000円台と3万9000円台にしている。年に2回のセール品では価格を下げて、さらに敷居を低くする。話題商品の発信では明るく伝えるのもコツだ。
またメディアの取材に協力的なのも、敷居の低さといえる。
「ある時期から『ウチがやっている活動をきちんと紹介しよう』と考えました」
多くのメディアに紹介されることで、ブランドへの理解が深まるとの思いからだ。例えば、出店する御殿場プレミアム・アウトレット店(2008年リニューアル開業)では、トラックに商品を積み込んで現地に向かうところからテレビクルーが取材に入った。
「スーパーブランドは取材お断りだったそうで、開業を伝えるニュース番組では、スコッチグレインの映像露出が多かったと聞きました」
被災地で測り続けた「1400人の足」
日本で暮らす人の価値観を変えた東日本大震災が起きた時、ヒロカワ製靴は、ecute上野店の出店準備中だった。震災後、まず新店に投入予定だった広告宣伝費500万円を取りやめ、義援金として贈る。
さらに「靴屋として、これから社会に出る人たちを靴で応援しようと考えました」
廣川さんは商品代金の4500万円分を贈ることを決意。3万円弱のスコッチグレイン1500足を「復興の靴」として、東北の新社会人にプレゼントすることにしたのだ。
つてを通じて東北大学のボランティアリーダーを知り、彼らと交渉を続けた末に、今年2月17日と18日の2日間、廣川さんをはじめとする社員6人が、同大学に足を運んだ。
スコッチグレインの靴選びは、足型の採寸から始まる。今回はソール素材も、雨や寒冷地の凍結した路面でも滑りにくい仕様を採用した。
「現地に行くと、すでに学生が200人ぐらい待っていてくれました。流れ作業で採寸をして靴を渡さないと時間内に終わらないので、5人が1組となり役割を決めてフル稼働。残りの1人は交代で休憩をとり、朝10時半から夜の7時まで続けました」
こうして初日に600足、2日目には800足を採寸し、学生たちにプレゼントしてきた。
3.11を経験した人たちは「(深刻な被害を思うと)自分はこんなことをしていていいのか」を自問し、多くの人が「自分ができることで被災地を応援しよう」と自答した。
廣川さんも例外ではなく、考えた末に「足元を支援」したのだ。
再び、東京ソラマチの店舗前――。開業日はあいにくの雨だったが、多くのお客が店を訪れていた。ヒロカワ製靴の公式サイトには、ソラマチ店オープンの告示がある。ここに記された宣伝コピーが同社の決意を示す。
「日本人が育んだ知恵と技を世界へ、未来へ、発信する」
「商品を製造販売するだけでなく、靴に関わるあらゆることを伝えたい」
これからもその意識で、足と靴に向き合い続けるのだろう。
■Company Profile
ヒロカワ製靴株式会社
・創業/1964(昭和39)年
・代表取締役社長 廣川雅一
・本社/東京都墨田区堤通1-12-11
(TEL) 03-3610-3737(代)
・事業内容/紳士靴・婦人靴の製造・販売
・代表商品/『スコッチグレイン』
・従業員数/140人(2012年4月30日現在)
・企業サイト http://www.scotchgrain.co.jp/
◆高井尚之(たかい・なおゆき)
ジャーナリスト。1962年生まれ。日本実業出版社、花王・情報作成部を経て2004年に独立。「企業と生活者との交流」「ビジネス現場とヒト」をテーマに、企画、取材・執筆、コンサルティングを行う。著書に『なぜ「高くても売れる」のか』(文藝春秋)、『日本カフェ興亡記』(日本経済新聞出版社)、『花王「百年・愚直」のものづくり』(日経ビジネス人文庫)、『花王の「日々工夫する」仕事術』(日本実業出版社)、近著に『「解」は己の中にあり 「ブラザー小池利和」の経営哲学60』(講談社)がある。




