人事評価の人材マネジメント上の公式な目的は、第1が、「処遇の格差付けに対する根拠の明確化」であり、第2が「育成指導ポイントの明確化」です。前者がいわゆる「査定機能」であり、後者が「育成機能」であって、人材マネジメントの向上のために人事評価をうまく活用することによって、企業の業績向上に貢献していくことが求められるわけです。
(1)処遇の格差付けに対する根拠の明確化
まず第1の目的についてですが、さまざまな評価項目で人事評価をすることになるわけですから、当然、被評価者本人の成果や能力、情意(態度)をしっかり評価することになります。そうなると、何がよくて何が悪いかが自ずと明確になり、その内容をしっかり把握すれば、処遇格差付けの根拠が分かります。そうなれば、自信を持って処遇格差を付けられるようになります。評価者のこの自信は、被評価者本人に対して、評価結果のフィードバックを根拠を示して行える自信でもあります。
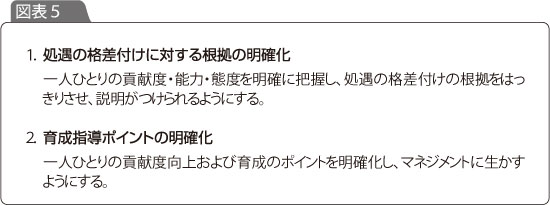
(2)育成指導ポイントの明確化
第2の目的は、人事評価結果の活用にかかわるものです。人事評価を処遇の格差付けだけに活用するのであれば、いかにももったいないことになります。ですから、人事評価の結果から分かった本人の強み・弱みは、実際の人材マネジメントに生かしていくようにしていく必要があります。
①育成機能としての生かし方
生かし方としては、①育成、②業務指導、③配置などです。もちろん、次期の目標設定につなげることは、言うまでもありません。
②「課題を考える」ことは人事評価の本質
「①育成」と「②業務指導」とは、同じことを言っているのではないかという見方もありますが、「育成」とは長期的に見ての「人づくり」を念頭に置いています。ビジネスパーソンとしての総合的な成果を目指すものです。それに対して「業務指導」とは、個々の業務のレベルを上げるために、スキルアップや業務態度の向上を行うためのものです。「③配置」とは、新しい経験を積ませるための異動政策のことを言います。これによって、業務経験の幅を広げようというものです。
「人事評価」と同じ意味合いの言葉に、「人事考課」があります。もともと、「人事考課」の「考課」という言葉は、「『課』を『考』える」、つまり「『課題』を『考』える」ということを意味すると言われています。いわゆる査定(=処遇の格差付けのための評価)だけではないのだぞ、ということを主張するために「人事考課」という言葉が使われたのです。考課という言葉が少し古めかしい印象を与えるので、本書ではもっと日常用語に近い「人事評価」という言葉を使っていますが、「『課題』を『考』える」という精神は受け継いでいます。そういう意味合いで、人事評価の人材マネジメント上の目的をとらえてください。
 この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円
この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円
(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)
 高原 暢恭(たかはら のぶやす)
高原 暢恭(たかはら のぶやす)
株式会社日本能率協会コンサルティング
取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント
1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。
HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。
著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)
『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。
また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。
http://www.jmac.co.jp/




