下山智恵子
インプルーブ社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士
変形労働時間制の原則、1カ月単位の変形労働時間制
今回のクエスチョン
Q1 変形労働時間制とは、どのような制度ですか?
A1 一定期間を平均して1週当たりの労働時間が法定内であれば、1日8時間、1週40時間を超えて働かせることができる制度です
原則として1日8時間、1週40時間を超えて働かせることはできないと前回説明しました。変形労働時間制とは、一定期間を平均して、1週当たりの労働時間が法定の労働時間以内であれば、1日8時間、1週40時間を超えて働かせることができる制度です。超えた時間は時間外労働にはならず、36協定の締結や割増賃金の支払いは必要ありません。
【解説】
1 変形労働時間制の原則
■週40時間を最大に活用できる
変形労働時間制は、労働時間を短縮することを目的として、認められるようになりました。労働者にとっては、暇な時期に会社に拘束されないところがメリットです。会社にとっても、法律に則(のっと)って導入すれば、週40時間の枠を最大に活用し、合法的に時間外労働手当を削減することができます。
変形労働時間制には、次の3種類があります[図表1]。
【図表1】 変形労働時間の比較
| 活用できる業務の特徴 | 対象業種 | 手続き | 労働基準監督署への届け出 | 1週間平均労働時間 | 労働時間の上限 | |
| 1カ月単位 |
・1カ月のうちでも日によって繁閑がある ・1日8時間を超える日がある |
制限なし | 就業規則に定める、または労使協定を締結する | 必要 | 40時間(特例事業場※は44時間) | 特になし |
| 1年単位 |
・特定の季節、月などに繁閑がある ・原則として土日曜休みだが土曜出勤の週がある ・1週40時間を超える週がある |
制限なし | 就業規則に定め、労使協定を締結する | 必要 | 40時間 | 1日10時間、1週52時間(3カ月を超える場合は48時間。このほか連続労働日数等に制限あり) |
| 1週間単位 |
・業務の繁閑が激しく、直前にならないと分からない |
小売店、旅館、料理店、飲食店で30人未満 | 労使協定 | 必要 | 40時間 | 1日10時間 |
※特例事業場は, 商業, 映画・演劇, 保健衛生業, 接客娯楽業で10人未満の事業場
2 1カ月単位の変形労働時間制の活用(労働基準法32条の2)
■1カ月以内の期間を平均して法定労働時間以内にする
1カ月単位の変形労働時間制は、1カ月以内の一定期間を平均して、法定労働時間の範囲内であれば、特定の日に8時間、特定の週に40時間(特例事業場は44時間)を超えて働かせることができる制度です。超えた時間は時間外労働として扱う必要がなく、36協定や時間外労働手当を支払う必要がありません。
例えば、月末が忙しく、月初が暇な会社であれば、月末の労働時間を長く設定したり、労働日数を増やすことができます。その分、月初の労働時間を減らすことで、1カ月の総労働時間を法定労働時間内に抑えるようにすればいいのです。
■「変形期間の法定労働時間の総枠」は簡単に計算できる
1カ月単位の変形労働時間制は、1カ月以内の一定期間を平均して週40時間以内にします。
「変形期間の法定労働時間の総枠」の計算式は、次の算式に当てはめて計算します。
対象となる期間は、1カ月以内であれば2週間、4週間など自由に定めることができます。
各変形期間の法定労働時間の総枠を計算したものが[図表2]です。変形期間を1カ月とする場合は、月による暦日数(30日、31日など)の変動にあわせて総枠が変動します。
【図表2】 各変形時間における法廷労働時間の総枠
| 変形期間 | 週40時間の事業場 | 週44時間の事業場 |
| 2週間(14日) | 80時間 | 88時間 |
| 4週間(28日) | 160時間 | 176時間 |
| 1カ月(30日) | 171.4時間 | 188.5時間 |
| 1カ月(31日) | 177.1時間 | 194.8時間 |
■他の制度よりも有利な点が多い
この制度は、特例事業場(商業、映画・演劇、保健衛生業、接客娯楽業で10人未満の事業場)の週44時間を最大に活用できる制度です。その場合、「週40時間」をすべて「週44時間」と読み替えて計算します([図表2]右)。
1年単位や1週間単位の変形労働時間制では、特例事業場でも週40時間で計算することに対し、1カ月単位の変形労働時間制では、週44時間で計算することができます。
また、1年単位の変形労働時間制では、1日の労働時間や1週の労働時間に上限が定められていますが、1カ月単位の変形労働時間制では上限が定められていない点も有利です。
■ある週が40時間を超えても時間外労働ではない
この制度を4週間単位で活用した例を考えてみます。ある週に50時間働かせた場合、変形労働時間制を活用しなければ、40時間を超えた10時間が時間外労働となります。
1カ月単位の変形労働時間制を活用すれば、40時間×4週=160時間が法定労働時間の総枠ですから、4週の総労働時間が160時間まで時間外労働ではありません[図表3]。
![[図表3] 1ヵ月単位の変形労働時間制の活用例](/data/readers/web_limited_edition/wp/images/20110531_shimoyama_001-3.jpg)
■1日8時間を超えても時間外労働にならない
変形労働時間制を活用すれば、1日8時間を超える所定労働時間を定めることができます。例えば[図表4]では、1日の労働時間は10時間ですから、このままでは違法になります。しかし、週40時間労働の範囲であるため、変形労働時間制を活用することで合法にすることができます。
![[図表4] 1日10時間で週休3日の場合](/data/readers/web_limited_edition/wp/images/20110531_shimoyama_001-4.jpg)
《復習&応用問題》
Q2 当社のパートの所定労働時間は、ほとんどの日が6時間ですが、忙しい時期だけ9時間としています。1週間をトータルすると40時間より短くなりますが、このような場合でも時間外労働手当を払わなければならないのでしょうか?
A2 変形労働時間制を活用すれば、時間外労働手当を支払う必要はなくなります
現状のままであれば、1日8時間を超える時間は時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要です。しかし、変形労働時間制を活用すれば払う必要はなくなります。
貴社の場合は、1カ月単位の変形労働時間制を1週間の変形期間としても活用できそうですが、1カ月の変形期間として賃金締切日に合わせておくほうが、時間外労働の時間管理が簡単にできると思います。
Q3 1カ月単位の変形労働時間制を活用する場合、どのような手続きが必要ですか?
A3 労使協定または就業規則に規定する必要があります
制度を活用するには、次のいずれかの手続きが必要です。
(1)労使協定を締結して労働基準監督署へ届け出る
(2)就業規則に規定する
いずれの方法でも、労働時間の定めとして就業規則に記載する必要があります。そのため、ほとんどの場合、労使協定によらずに就業規則に規定することによって導入しています。労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は過半数を代表する者と締結します。
就業規則または労使協定には、各日の始業・終業時刻を定めなければならず、その日の業務の都合によって、会社が任意に変更するような制度には使えません。
就業規則で指定することが難しい場合は、シフト勤務表による方法もあります。この場合、就業規則には次の項目を記載しておきます。
(1)始業・終業時刻の勤務パターン
(2)勤務の組み合わせの考え方
(3)シフト勤務表の作成方法と周知方法
Q4 1カ月単位の変形労働時間制を導入した場合、時間外労働の時間はどのように計算すればいいですか?
A4 法定の時間外労働を[図表5]のように計算しますが、多くの会社では、所定労働時間を超えた時間に対して割増賃金を支払っています
法定の時間外労働を計算して支払うことになりますが、計算はかなり複雑です。
通達では、[図表5]上段のようになっています。しかし、通達どおりに計算すると、かなり複雑になります。そのため実務としては、多くの会社で法定時間外労働と所定時間外労働を厳密に区別することなく、あらかじめ定めた所定労働時間を超えた時間に対して割増賃金を支払っています。このようにすれば、法定時間外労働に対しては必ず割増賃金を支払うこととなり、法違反が生じることはありません。
![[図表5] 1ヵ月単位の変形労働時間制における時間外労働の考え方](/data/readers/web_limited_edition/wp/images/20110531_shimoyama_001-5.jpg)
※本記事は、人事専門資料誌「労政時報」の購読者限定サイト『WEB労政時報』にて2011年6月に掲載したものです
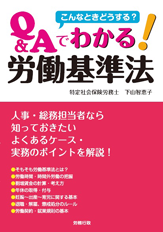
|
こんなときどうする? Q&Aでわかる! 労働基準法 ●人事・総務担当者なら知っておきたい、よくあるケース・実務のポイントを123問のQ&A形式で解説! ●労働時間、解雇、賃金など、問題となりがちな項目について、労働基準法の定め・取り扱い等を図解入りで解説 第1章 労働基準法とは? |
 下山智恵子 しもやまちえこ
下山智恵子 しもやまちえこ
インプルーブ社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士
大手メーカー人事部を経て、1998年に下山社会保険労務士事務所を設立。以来、労働問題の解決や就業規則作成、賃金評価制度策定等に取り組んできた。 2004年には、人事労務のコンサルティングと給与計算アウトソーシング会社である(株)インプルーブ労務コンサルティングを設立。法律や判例を踏まえたうえで、 企業の業種・業態に合わせた実用的なコンサルティングを行っている。著書に、『労働基準法がよくわかる本』『もらえる年金が本当にわかる本』(以上、成美堂出版)など。
http://www.improve1998.com/




