下山智恵子
インプルーブ社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士
今回のクエスチョン
Q1 祝日に労働者を働かせた場合、割増賃金を払わなければなりませんか?
A1 祝日だからという理由で割増賃金を払う必要はありません
祝日は法律で定められた休日ではありません。
そのため、祝日に働かせても割増賃金を払う必要はありません。
【解説】
■法定の労働時間は1日8時間、週40時間
法定労働時間は次のように定められています。
①一般の事業場
1日8時間または1週40時間を超えて働かせることはできない
②特例事業場(商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で10人未満の事業場)
1日8時間または1週44時間を超えて働かせることはできない
この時間を超えて労働させるためには、変形労働時間制等によって働かせる場合を除いて、時間外・休日労働に関する協定届(36協定)の締結、届け出と割増賃金の支払いが必要です。
時間外・休日労働を含まない「所定労働時間」は、1日8時間と1週40時間(一般の事業場の場合)の両方を満たす必要があります[図表1]。
なお、この場合の1日とは、午前0時から午後12時までをいいます。1勤務が2暦日にまたがる場合は、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として扱い、その勤務は始業時刻の属する日の労働として「1日」の労働とします。また、1週は、就業規則などに定めがない限り、日曜日から土曜日までをいいます。どの7日間をとっても40時間以内である必要はありません。
![[図表] 1日8時間と1週40時間の考え方(一般の事業場の場合)](/data/readers/web_limited_edition/wp/images/20110517_shimoyama_01.jpg)
■休日は4週4日(労働基準法35条)
労働基準法では、休日は、毎週1日または4週に4日与えるように定められています。4週4日の場合は、就業規則等で4週の起算日を明らかにするものとし、どの4週を区切っても4日与えなければならないものではありません。
例えば、土曜日、日曜日が休みの完全週休2日制の会社では、1日は法定休日ですが(例えば日曜日)、後の1日(例えば土曜日)は法定休日ではありません。ただし、この会社が1日8時間労働だとすると、土曜日に勤務させた場合、その労働は週40時間を超える労働ですから、時間外労働になります。
■休日は暦日で与える
休日は、原則として午前0時~午後12時の暦日で与えます。前日の残業が午前0時に食い込んだり、翌日の早出勤務が午後12時以前になったりした日は、休みを与えたことになりません。ただし、3交替勤務などの場合は、継続した24時間を1日と認められることがあります。
■年末年始に休ませる義務はない
年末年始やお盆、祝日などは法律で定める休日ではありません。4週4日の休日を与えていれば、これらの日に働かせても、休日労働手当を支払う義務はありません。
休日に関する決まりは、以下のとおりです。
○国民の祝日、年末年始、お盆休み等に休ませる義務はない
○週休2日制は義務づけられていない
○完全週休2日制の会社で、日曜日を法定休日とすれば、土曜日の労働は法定の休日労働ではない
○何曜日を休日にしても構わない
○週によって休日の曜日が異なってもよい
○従業員によって休日が異なってもよい
■労働時間は会社の指揮命令の下に働く時間
「会社の指揮命令の下に労働する時間」が「労働時間」です。休憩時間は労働時間ではないので、拘束時間から除きます[図表2]。
[図表2] 労働時間の判断例
| 労働時間(例) | 労働時間ではないもの(例) |
○会社の指示の下に行う、作業前の準備や後始末 ○出席が義務づけられている研修 ○法令で義務づけられている安全衛生教育 ○エックス線利用者など、有害な業務に従事する者に行われる「特殊健康診断」 ○手待ち時間(例えば、来客が来るのを何もしないで待っている時間) |
○出張の往復時間(ただし、物品の監視等を伴う場合は労働時間) ○自由参加の研修 ○労働者一般に行われる「一般健康診断」 |
《復習&応用問題》
Q2 当社では、労働者のスキルアップのために、休みの日に社外へ研修に行かせています。研修費用は会社が負担していますが、時間外・休日労働手当を払っていません。問題ありますか?
A2 参加を命じている場合や仕事に密接な関連がある場合は、時間外・休日労働手当が必要です
研修に参加するよう命じている場合は労働時間です。特に命じていない場合でも、仕事に密接な関連があるもので使用者が用意した研修であれば、労働時間になります。
一方、自由参加であることがはっきりしている場合は、労働時間ではありません。この場合は時間外・休日労働手当を払う必要はありません。
Q3 当社では、他府県への出張に際し、仕事を終えてから移動することが多いですが、時間外労働手当は必要ですか?
A3 出張の移動時間に対して、時間外労働手当を払う必要はありません
出張で移動する時間は、拘束はされていますが労働者の自由な時間であり、労働時間ではありません。ですから、時間外労働手当を払う必要はありません。ただし、物品を運ぶなど移動中も物品を監視する必要がある場合は、労働時間になります。
※本記事は、人事専門資料誌「労政時報」の購読者限定サイト『WEB労政時報』にて2011年5月に掲載したものです
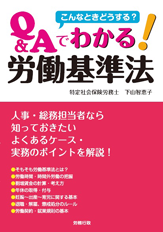
|
こんなときどうする? Q&Aでわかる! 労働基準法 ●人事・総務担当者なら知っておきたい、よくあるケース・実務のポイントを123問のQ&A形式で解説! ●労働時間、解雇、賃金など、問題となりがちな項目について、労働基準法の定め・取り扱い等を図解入りで解説 第1章 労働基準法とは? |
 下山智恵子 しもやまちえこ
下山智恵子 しもやまちえこ
インプルーブ社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士
大手メーカー人事部を経て、1998年に下山社会保険労務士事務所を設立。以来、労働問題の解決や就業規則作成、賃金評価制度策定等に取り組んできた。 2004年には、人事労務のコンサルティングと給与計算アウトソーシング会社である(株)インプルーブ労務コンサルティングを設立。法律や判例を踏まえたうえで、 企業の業種・業態に合わせた実用的なコンサルティングを行っている。著書に、『労働基準法がよくわかる本』『もらえる年金が本当にわかる本』(以上、成美堂出版)など。
http://www.improve1998.com/




