大野 順也 おおの じゅんや
株式会社アクティブ アンド カンパニー 代表取締役
1.予想できない経済環境
少子高齢化やIT技術の飛躍的な進歩などにより現在の日本経済は、だれもがこれまでに経験したことのない市場環境・社会構造の変化に直面している。また、2008年9月のリーマン・ショックを発端とした世界規模での不況、先日発生した東日本大震災の影響など、今の日本はかつてないほどの大きな変化の前に立たされているといえるだろう。
しかし、このような未曾有の環境変化を目の前にして、どのように対応すればよいのか、また、どのように切り抜けていくのかを考えあぐねている企業は多い。特に中堅・中小企業では、昨今の環境変化に際して打開策を打てず、今後の展望に対して行き詰まりを感じているというケースも少なくない。
この行き詰まり感の原因は、少子高齢化に伴う国内市場の縮小、IT技術の進歩などによる市場環境の変化の速さなど、さまざまな外的要因が作用していると考えられる。しかし、そうした企業に共通していえることは「既存の事業内容を所与のものとしていること」である。あくまでも"既存事業ありき"で自社の将来を考えていることが、そもそもの原因といえるだろう。すなわち、市場環境が変化しているにもかかわらず、「自らの企業価値とは何か」といった自社の内的要因を見つめる視点が変化していないために、そこに現実とのズレや乖離が生じており、結果として、明確な対策が構想できないのである。
いま求められているのは、既存事業によって「過去に生んだ価値」よりも自社の強みを再確認し、それを活かすことで実現される「将来生む価値」に着目することである。そのことを事業価値転換(バリュートランスフォーメーション、略してVT)と呼ぶ。
2.企業自身の自社に対する認識
そもそも自社にとって「企業価値」とはなんであろうか。
企業価値とは、"企業の事業活動やそれらの成果・結果などがもたらす効用や値打ちを、ステークホルダーが評価したもの"と定義できる。したがって、企業価値は、おおむね既存の事業内容に対するそれぞれのステークホルダーの評価によって決まってくる。この既存の事業内容に沿って企業を見る目線が、事業価値転換を阻んでおり、自社の将来を思い描く際の盲点となっている場合が少なくない。
つまり、ステークホルダーからみられる既存の事業内容に沿った評価の目線が、組織・社員、また企業そのものに対して既成概念を生み、企業の事業アイデンティティを定義し、その形成されたイメージが揺ぎないものとして固定化されてしまっているわけだ。
例えば、「我が社は、○○の事業が屋台骨を担っており、○○の製品でお客様に喜んでいただいている」といったように、固定観念を前提にすると、既存の事業内容を見直し、新しい事業価値を創出する、転換するといった視点は、組織や社員に形成されづらい。
3.事業価値転換の例:富士フイルム
しかし、そのような環境下においても、事業価値転換を実現しようとしている企業がある。近年の活動で記憶に新しいのが富士フイルムである。
同社は、これまでフィルム事業を中心に成長・発展を遂げてきた。しかし、近年のデジタルカメラ市場の台頭によって、フィルム事業の縮小を余儀なくされた。そのような中、同社は、これまでのフィルム事業によって培った"フィルムの酸化防止技術"や"原材料であるコラーゲンを扱う技術"を用いて、ヘルスケア事業に進出し、新しい事業アイデンティティを形成しようとしている。
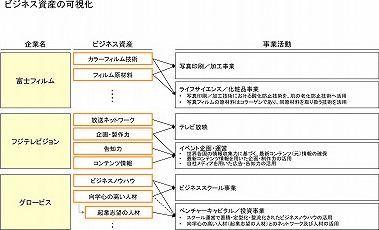
同社のような取り組みは他に例がないわけではなく、富士重工業(スバル)の自動車業界への参入や、3Mの低粘着接着剤の活用によるポストイットの開発など、歴史を紐解くと、自社の有する技術に新たに視点から光りを当て、それを外的環境の変化に合わせて再構築していく取り組み事例はいくつも出てくる。大きく成長している企業は、概してこのような事業転換を果たして成長してきているといっても過言ではない。

ではなぜ、多くの企業がこういった事業転換を果たすことができないのか。それは前段で述べた事業内容に沿って企業価値が評価されていることによる弊害はもとより、経営者の過去の成功体験による弊害や、自社が保有しているビジネスの源泉となる資産の理解不足などが挙げられる。
4.事業価値転換を促進(バリュートランスフォーメーション、略してVT)とバリュートランスフォーメーションとは
一般的に、企業が扱う商品・サービスには、導入期→成長期→成熟期→衰退期(転換期)というライフサイクルがある。
この転換期に差し掛かった企業は、意識的に事業価値転換を図らないと、ずるずると衰退していくだけである。そこで必要となるのが事業転換である。当社では、事業価値転換コンサルティング、バリュートランスフォーメーションコンサルティング(以下、VTC)を提供している。VTCでは、これまでに企業が保有している本質的な価値(ビジネスの源泉となる資産)を"ビジネス資産"と呼ぶ。ビジネス資産は単に財務的な指標とは違い、事業活動において価値を生み出す源泉になっているビジネスモデル、製造技術、特許、運営ノウハウ、企業文化、その会社特有の思考や行動様式なども含めた広い概念である。
自社にとっては、当たり前すぎて見過ごされがちなビジネス資産を外部の視点から抽出し、その次世代の成長の"種"をもって新たな事業活動への転換を促進していくことで、企業の事業価値転換を実現していこうというわけだ。
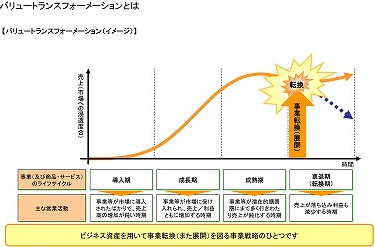
VTCは、これまでに保有している(また形成してきた)ビジネス資産を用いて、事業価値の転換を図るため、具体的かつ実効性の高い事業価値転換の戦略を立案することができる。
他のコンサルティングサービスとVTCの大きな違いは、既存の事業を基盤としてプロジェクトは進めるものの、変えることのできない"所与のもの"としないことである。つまり、既存の事業を下支えしている、また既存の事業を通して形成された"ビジネス資産"に着目し、その"ビジネス資産"を明らかにすることを通して、新しい事業の形成につなげていくところにある。企業は表層的な"ビジネス資産"は理解しているものの、その深層にあるビジネスの本質的な部分に寄与する"ビジネス資産"に気が付いていないケースが多い。
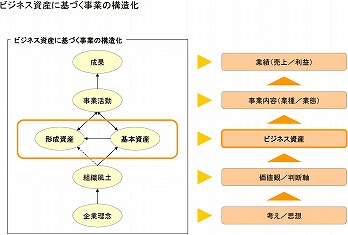
自社におけるビジネス資産を明確にしておくことは、事業価値転換を目前に控えた企業においては急務課題であるが、目まぐるしく変化する市場環境・社会構造に対して、発展・成長していくうえでも必要な考え方といえるだろう。
※次回は2011年5月27日に掲載します。
バリュートランスフォーメーションコンサルティングに関する詳細は、下記のサイトをご覧ください。
http://www.aand.co.jp/consulting/transform.html

Profile
大野 順也 おおの じゅんや
株式会社アクティブ アンド カンパニー 代表取締役
1974年兵庫県生まれ。大学卒業後、株式会社パソナに入社。営業部を経て、営業推進室及び営業企画部門を歴任。アウトソーシングに関わるコンサルティングから同社関連会社の立ち上げを手掛ける。その後に、現デロイト トーマツ コンサルティング株式会社にて、組織・人事コンサルティングに従事し、2006年に株式会社アクティブ アンド カンパニーを設立し、代表取締役に就任。現在に至る。




