中川繁勝 なかがわしげかつ エスジェイド代表、人財育成プロデューサー
「受講者が受け身になっている」というのは、多くの育成担当者が抱える悩みの一つであろう。“受講者にいかに主体的に研修に関わってもらうか”という課題に、研修を作る側も、提供する講師も、もちろん育成担当者も同じように取り組んでいる。今回は受講者に主体性を持たせる学習方法について紹介する。
●研修に対してネガティブな参加者に、「参加してよかった」と言ってもらうためには
残念ながら喜んで研修に参加するという人は多くはない。「仕事が忙しい」「仕事を優先させたい」「仕事を抜けられない」などのさまざまな理由で研修参加を辞退する人がいる一方で、研修に参加する意味を見いだせないまま席に着いている人もいる。あるいは、「これで1日ゆっくりできる」「話を聞きながらまとめてメールの処理をしてしまおう」などと考える人もいるだろう。
しかし、そんな状況であっても、参加者が研修に興味を持ち、主体的に取り組み、気づきや学びを持ち帰って、「参加してよかった」と言ってもらえるとしたら、それは育成担当者としての喜びだ。もちろん、その気づきや学びを業務で生かしてもらえてこそ、育成担当者としてのミッションの達成と言えるだろう。
参加者が主体的に研修に取り組むために、発問(発表者が聞き手に質問を投げかけること)して発言してもらったり、ペアワークやグループワークをしてもらったり、発表してもらったりすることは多い。それはそれで効果は出るのだが、根本的な仕組みから上記の効果を実現する手法はないものだろうか。
●e-Learning教材の進化と設計理論
私は過去にe-Learningの開発に関わったことがある。当時はまだe-Learningの黎明(れいめい)期で、ネットワーク環境も現在ほど整っておらず、PCもスピーカーがついているものが少ない時代だった。そのため、e-Learningといっても、単なる紙のテキストブックをHTMLに置き換えたような代物であった。
今では効果的なe-Learningの開発手法が研究され、数々の魅力的なコンテンツが登場している。情報技術の進化による貢献も大きいが、インストラクショナルデザイン(ID)という学習コンテンツを設計するための考え方が確立・浸透し、実際に適用されてきたおかげだ。
[注]インストラクショナルデザイン:学習者の自由度を担保しながら高い学習効果を生むために、学習ニーズ分析、システマティックな教材設計などを行うこと。
このIDの理論の一つにゴールベースシナリオ(GBS)理論がある。
GBS理論とは、問題解決型の学習アプローチの一つで、行動することによって学ぶ教材を設計するための学習理論だ。このGBS理論を使った学習教材にはシナリオがある。まずは学習者が使命を達成したいと思わせるような状況設定が「カバーストーリー」(導入部分における説明)として提示される。学習者はそのストーリーの中で主人公となり、重要な役割が指定されるのだ。もちろんそのストーリーも主人公としての役割も、現実的なものとなる。そこから数々の問題に直面するようなストーリーが展開していく。それらを解決していく過程で学習対象となるスキルを自然と学び、身につくように設計されているのだ。この学習理論を活用した学習方法はストーリーベースド・ラーニング(SBL:Story-based Learning)と呼ばれ、主にe-Learning教材において広く活用されている。
SBLを簡単に表現してしまえば、コンピューターゲームの一種であるロールプレーイングゲーム(RPG)だ。RPGでは、プレーヤーはある状況設定の中での主人公となり、ゲーム内のキャラクターを操りながらゲームの中に展開される世界を動き回り、仲間と出会い、敵と戦い、経験値や戦闘力を高めながら強いキャラクターへと成長し、ゴールへと向かう。途中、謎(なぞ)解きが求められたり、複数の選択を迫られたりしながら進んでいく。異なる選択によって異なる場面が展開されることもある。
どうやらこのストーリーベースの進め方というのは、コンピューターを使ったゲームや学習教材にはうまく適用できているようだ。
●自分が主役!
さらに、ストーリーで進んでいくというのは、面白みがある。なんと言っても自分が主役であり、自分の判断によって展開が変わる。疑似体験ができるのだ。そう、SBLは一種のシミュレーションなのだが、シナリオ形式になっているため、一連の業務の中で必要な知識やスキルを動員しながら経験することができる。
SBLのようにシナリオをベースに学ぶことは事例学習の一つの手法だ[図表1]。同じく事例学習の一種である“ケーススタディ(実際に起きた事例を研究すること)”は、やや客観的になってしまうという意味で、参加する面白みがSBLより薄いと言える。また“シミュレーション”では、時間軸や状況を狭い範囲で設定するため、スキルセット(必要な知識や技能)も絞られる。
SBLは、ケーススタディの“状況設定”とシミュレーションの“疑似体験”をうまく組み合わせて学習者を主体的にする、効果的な学習アプローチであると言える。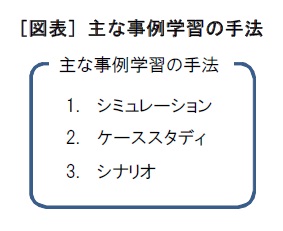
●国連の提供している学習ゲーム
国連がWebで面白いSBLの教材を提供している。国連で唯一の食糧支援機関であるWFP(World Food Programme:世界食糧計画)が提供している、「フードフォース(Food Force)」というゲームがそれだ。
「フードフォース」はWFPの緊急食糧支援活動を疑似体験することができるゲームなのだが、プレーヤーはこのゲームをプレイすることで、WFPが行っている人道支援活動を知ることができるようになっている。よくできたCGと音声による解説や指示のおかげで、世界の一部で起こりつつある深刻な危機を知り、そこに立ち向かうWFPの活動の広さと困難さを知ることができる。単なる知識であれば、文章で読んで知ることも可能だが、ゲームをプレイすることで判断の難しさや立ち向かう困難さを感じることができるという点で、プレーヤー(学習者)に与える影響はまったく違うものと言えるだろう。
実際に中学1年生の息子にプレイしてもらった。食糧支援のミッションと知って、単に食料を貧困地域に車で運ぶ程度と思っていた彼だが、何をどれだけ運ぶのか、どこに、どうやって運ぶのかまでも考えなければならなくなり、難しさを感じていた。同時に、WFPの活動が単に食料を運ぶことにとどまらず、その土地の復興に貢献することも知ることとなった。遊んでいるようで実は世界のどこかで行われているWFPの活動を学んでいたのだが、当の本人は「勉強している」という感覚ではなく、ミッションをクリアすることに必死――という、まさにゲーム感覚だった。もちろん、社会科の教科書を開くよりも集中して取り組んでいたのは言うまでもない。
●早稲田大学の統計学学習
また、早稲田大学の人間科学学術院の向後千春先生は、学生が敬遠しがちな統計学を学ばせるために、ストーリーベースのe-Learning教材を開発した。
統計学というのは調査データの解析に必要であり、大学の基礎教育の一端を担う科目であるが、講義中心では学生の興味を引くことができず、また手法を学ぶための部分的な実習では作業の意味が欠落してしまうという課題があった。そこで、身近な設定でのストーリーを用いて独習できるWeb教材を使うことで、効果を上げている。
●社会人基礎力の養成にも
また、近年では、ストーリーベースのe-Learningは学生向けの社会人基礎力の養成にも活用されている。学生たちがゲーム感覚で社会人基礎力を磨くために、キャンパスの場でどう社会人基礎力を発揮するかという「キャンパスライフ編」、就職後に新入社員としてどう発揮するかという「フレッシュマン編」というシナリオが用意されている。さらに職種についても「商社編」「情報システム担当者編」「建設会社営業編」など幅広く設定されている。
シナリオに沿って与えられるさまざまなシチュエーションの中で、プレーヤーである学習者が考え、課題(設問)に対して最適と思われる選択肢を選ぶようになっている。各設問は社会人基礎力の12の項目に沿っており、最終的には「スキル診断」として社会人基礎力の三つの能力である(1)前に踏み出す力、(2)考える力、(3)チームで働く力――のスキル度合いがグラフで、さらにそれぞれを細分化したスキルがレーダーチャートで表現されるのだ。
学生は、ストーリーで設定される状況に入り込みながら、自分の立場から考え判断することができるので、判断もしやすくなり、診断の結果も真実に近い数値が出てくるものと思われる。また、職場のシナリオを進めるにつれて社会人基礎力の必要性を深く知ることとなる。
●集合研修での活用の可能性
そもそもGBS理論は、e-Learning教材の開発の理論として発展してきているのだが、この手法は集合型の研修にも適用ができるのではないかと思う。多くの研修が学習項目別の研修プログラムで構成されているが、GBS理論に基づく集合研修では、まず受講者の業務に合ったストーリーを準備し、その業務ストーリーを進めていく中で、必要な要素を学び、考え、話し合っていく形となる。その中で受講者は、本当に必要な知識やスキルを知るとともに、その必要性を深く感じることができるであろう。「研修が業務に直結しない」というような、受講者や現場リーダーたちの不満解消にもつながるかもしれない。
育成担当者としては、GBS理論のようなアカデミックな理屈も押さえつつ、学びの場への応用を考えていきたい。
※本記事は、人事専門資料誌「労政時報」の購読者限定サイト『WEB労政時報』にて2011年11月に掲載したものです
 中川繁勝 なかがわしげかつ エスジェイド代表、人財育成プロデューサー
中川繁勝 なかがわしげかつ エスジェイド代表、人財育成プロデューサー
システムエンジニア、ネットワーク技術者養成のマーケティングを経て、ITコンサルティング会社の人財開発マネジャーとしてコンサルタントの育成に従事した後、独立。現在は、研修講師としてロジカルシンキングやプレゼンテーション等のコミュニケーション系研修を提供するとともに、人財育成を支援するためのコンサルティングサービスも提供している。NPO法人人材育成マネジメント研究会理事。ワールド・カフェをはじめとした対話の場の普及を促進するダイナミクス・オブ・ダイアログLLPのパートナーとして、各種ワールド・カフェとワールド・カフェ・ウィークの開催を推進。また、場活流チェンジリーダー塾にてメンターとしてリーダーの在り方を養成する活動にも従事する。




